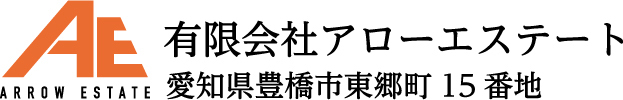相続・不動産(土地・家)の売却は、豊橋のアローエステートまで

HPはこちらへ
空き家
空き地を
有効活用しませんか?
相続登記の義務化が令和6年4月1日よりスタートしました。
相続登記の義務化について再度確認します。
相続登記の義務化とは?
土地や建物を相続する人(相続人)は、不動産(土地・建物)の名義を変更する手続きをします。これが「相続登記」です。
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

相続登記が義務化されるのはなぜなのでしょうか?
「所有者不明土地」の問題があります。
「所有者不明土地」とは、不明または判明しているものの、所有者と連絡がつかない土地です。
「所有者不明土地」が生み出される原因は、相続登記(66%)、住所変更登記(34%)の未了とのことです。(国土交通省調査)
相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない土地が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の義務化が始まるのは、いつから?
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。
ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
いつまでに相続登記をすればいいの?
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
まとめ
山間部や中小都市は、最後の登記が50年以上経過した土地もあり、都市部への人口流出や地価低迷に伴い、親の死後に子らが「手間がかかる」「管理できない」などとして放置されてきた面もあるとみられます。
不動産登記簿などでは新たな持ち主が分からなかったり、判明しても連絡が取れなかったりする所有者不明土地は全国的に増えています。
東日本大震災の被災地では、集団移転先となる高台の山林に所有者不明の土地が相当数見つかり、所有者特定に時間を要したため復興に遅れが出たことも。
被災地に限らず、公共事業や再開発では用地買収交渉に支障を来す恐れがあります。
防災や街づくりの点でも所有者不明土地を減らしていく必要があると思います。
または、「土地は相続した。。または、これから相続する予定があるが、土地の使いみちは決まっていない。」
相続登記をしても、空き地・空き家のままで無駄な税金を支払い続けなければならず、これは大きな損失です。
相続人にはデメリットしかありません。
思うように管理するのが難しく、そのまま放置されてしまっている土地が多くなっています。
遠く離れた田舎の土地を相続した場合などは、そうなってしまいます。
所有者不明土地を無くすため、国は法律で、打開しようとしています。
私たちも、相続する予定の不動産、または相続した不動産の未来について考えてみませんか?
分からない事で不安になる事もあるかと思います。そうした分からない事を親切・丁寧にお伝えしていき、お客様の不安を少しでも解消し、笑顔にできるようアローエステートは、努めます。